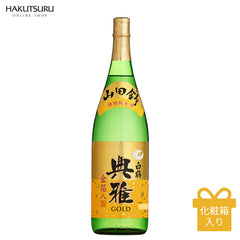お屠蘇とは?由来や中身を解説!誰でもできる簡単な作り方も紹介
Share
お屠蘇(とそ)とは無病息災や長寿の願いを込めてお正月に飲む祝い酒のことです。
今回の記事ではお屠蘇の由来や中身、作り方を解説しています。
- 白鶴酒造オンライン編集部
白鶴酒造が運営する「白鶴オンラインショップ」の編集部。
メンバーは研究開発と商品開発を経験した2名で構成。
開発担当時に得た知識を活かして、日本酒のちょっとした知識や楽しみ方、季節にまつわる情報をご紹介します。
「日本酒に興味はあるけれど、なんだか難しい~!」という声を少しでもなくすべく、分かりやすい情報を発信していきます!
お屠蘇とは?いつから飲まれているの?

お屠蘇とは無病息災や長寿を願ってお正月に飲む祝い酒のことです。
お屠蘇の由来は諸説ありますが、古くから多くの日本人に親しまれてきました。ここではお屠蘇の由来や歴史を解説します。
お屠蘇の歴史

お屠蘇の発祥の地は中国です。
諸説はありますが、三国時代の名医である華佗(かだ)が数種類の生薬を調合してお酒に浸し、災難厄除けのために飲んだことが始まりといわれています。
中国から日本に広まったのは平安時代です。
中国の博士である蘇明(そめい)が使者として朝廷を訪れた際に屠蘇散(とそさん)を献上しました。
天皇が屠蘇散をお酒に浸して飲んだことから宮中のお正月行事でお屠蘇を飲むことが定着しました。
江戸時代になると医者が薬代のお返しとして屠蘇散を配るようになり徐々に一般庶民にも広まったと言われています。
現在でも年末になると屠蘇散を配る薬局などがあります。
お屠蘇の由来
お屠蘇の由来は諸説あり、地域や家庭などによって解釈が異なるようです。
どの由来も悪いものを屠(ほふ)るという意味があり、無病息災や長寿を願う祝い酒として定着しています。
由来のひとつに「邪気を屠り、魂を蘇生する」という意味からお屠蘇という言葉が生まれたという説があります。
ほかには「病気や災いをもたらす鬼である蘇を屠る」という意味からお屠蘇という言葉になったという説もあるようです。
お屠蘇を飲む時期は?

先述したとおり、お屠蘇とはお正月に無病息災や長寿の願いを込めて祝い酒として飲むものです。
お正月を過ぎたころに「お屠蘇気分」という言葉を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
ここでは、お屠蘇を飲む正しいタイミングやお屠蘇気分という言葉について解説します。
お屠蘇はいつ飲むのが正しい?

お屠蘇を飲むタイミングは元旦、つまり元日の午前中、雑煮やおせち料理を食べる前が正しいとされています。
家族がそろって新年の挨拶をしたあとに飲みましょう。
また、正月の三が日、つまり1月1日〜1月3日の間に来客があった場合にもお屠蘇をすすめて新年の挨拶を交わすことが礼儀とされています。
お屠蘇気分とはどのような気分?
最近では使用されることが少ないかもしれませんが、正月特有の浮かれた気分を表すお屠蘇気分という言葉があります。
正月はお祝いする雰囲気に包まれており、めでたさからだらだらと過ごしてしまうという人は多いのではないでしょうか。
正月が過ぎても浮かれた気分が続き、なかなか気持ちが切り替わらないことがあります。
正月休みが終わり、仕事や学校がはじまっても気分が浮かれていることはありませんか?
そのようなときに「お屠蘇気分が抜けない」などと表現します。
お屠蘇の中身は何?

お屠蘇は数種類の生薬を配合した屠蘇散をお酒に漬け込んだ薬用酒です。
屠蘇散に配合される生薬の種類や数に決まりはありません。
一般的に屠蘇散には5〜6種類、多いものでは10種類ほどの生薬が配合されています。
また、地域によって漬け込むお酒の種類が異なることもあるようです。
代表的な生薬の種類や地域による中身の違いを紹介します。
お屠蘇の中身

一般的なお屠蘇の中身は屠蘇散と日本酒、みりんです。
お屠蘇の材料である屠蘇散に使用される生薬はさまざまです。
代表的な生薬として、山椒(サンショウ)や桔梗(キキョウ)、桂皮(ケイヒ)、白朮(ビャクジュツ)、陳皮(チンピ)、防風(ボウフウ)などがあります。
地域により異なるお屠蘇の中身
中国から広まったお屠蘇はお酒に屠蘇散を浸したものですが、現在では地域によって異なった中身のものがお屠蘇としてそれぞれ定着しています。
関西では日本酒にみりんを加えた甘めのお酒に屠蘇散を漬け込んだものをお屠蘇と呼んでいます。
一方、関東から北では屠蘇散は使用せずに日本酒そのものをお屠蘇としていることが多いようです。
また、九州では地酒を使用することがあるようです。
熊本では赤酒、鹿児島では黒酒という灰持酒(あくもちざけ)に屠蘇散を漬け込みます。
灰持酒とは日本酒の一種であり、醸造したもろみに木灰を投入することによりお酒の保存性を高めたものです。
お屠蘇のアルコール度数
お屠蘇には日本酒やみりん、灰持酒などさまざまなアルコールが使用されます。
使用するアルコールの種類によってお屠蘇のアルコール度数は異なってきますが、一般的には15%前後と考えてよいでしょう。
20歳未満の人や運転の予定がある人は口につけずに飲むふりだけにしてください。
お屠蘇を飲むときの作法は?

お屠蘇を飲むときには作法があります。
無病息災や長寿の願いを込めて正しい作法でお屠蘇を飲みましょう。
地域や家庭によっては作法が異なることもあるようです。
ここでは、基本的な作法や地域や家庭により異なる作法について紹介します。
基本的な作法

基本的な作法はまず家族全員が日の出の方向である東を向きます。次に最年長者が最年少者の酒器にお屠蘇を注ぎます。
お屠蘇を注ぐ酒器は屠蘇器と呼ばれる大・中・小の三段重ねの盃を使用しましょう。お屠蘇を注ぐときは飲む人の右側から注いでください。
お屠蘇を注いだあとは最年少者から最年長者へと順に飲んでいきます。小さい盃から大きい盃の順に1杯ずつ3回に分けて飲むことが基本です。
お屠蘇を飲むときには無病息災や長寿の願いを込めて「一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一里病なし」と唱えます。
最年少者から最年長者へと順番に飲み進めるのは年少者の活発な生気を年長者が飲み取るという意味や年少者が毒味をする役割があるといわれています。
厄年の人は年齢に関係なく最後に飲みましょう。厄を払う力を家族に分けてもらうという意味があります。
ちなみに、屠蘇器がない場合は、お正月にふさわしい酒器で代用しましょう。1つの酒器を使用して1杯ずつ3回に分けて飲んでください。
地域や家庭により異なる作法

地域や家庭により作法が異なることもあります。
基本的な作法では最年少者から最年長者へと順に飲んでいきますが、反対に最年長者から最年少者へと飲みすすめる地域や家庭もあります。
年長者が年少者に英知を分け与えるという意味があるようです。
また、屠蘇器を1人で3つ使用せずに大きい盃は父親、中間の大きさの盃は母親、小さい盃は子どもと使い分けることもあります。
お屠蘇を家で作る方法は?

お屠蘇は材料があれば家でも簡単に作ることができます。
材料も簡単に手に入るので自分でお屠蘇を作ってみてはいかがでしょうか。
お屠蘇に必要な材料や作り方を紹介します。
お屠蘇に必要な材料

お屠蘇に必要な材料は屠蘇散と日本酒、本みりんの3つです。
屠蘇散はパック入りのものが酒屋やスーパー、ドラッグストア、ネットの通販サイトなどで購入できます。
先述したとおり、屠蘇散に配合されている生薬の種類や数はさまざまです。好みの生薬が配合された屠蘇散を探してみましょう。
また、みりんは本みりんを選ぶことが大切です。
みりんには本みりん、みりん風調味料、みりんタイプ調味料の3種類があります。みりん風調味料はアルコールがほとんど入っておらず、みりんタイプ調味料は塩分が含まれています。
みりんに限らず日本酒もですが、良質なものを選ぶことが良い味のお屠蘇を作るポイントです。
お屠蘇の作り方

お屠蘇の作り方はまず日本酒と本みりんを合わせて180ml準備します。
次にパックに入った屠蘇散を1包漬け込み5〜8時間ほど待ちます。
パックを漬け込む時間は屠蘇散のパッケージに記載されている時間を目安にしましょう。
漬け込みすぎると濁りや沈殿物が出てしまう可能性があります。
また、日本酒と本みりんの配合は甘さや口当たりを確認しながらお好みで調節してください。
日本酒が多い場合は辛口になり、みりんが多い場合は甘口でまろやかになります。
季節のお酒を飲んでみよう
お正月が近づくと目にする機会も多くなる「お屠蘇」という言葉。
どういったものなのか、どんな作法があるのかなど、ご理解いただけたかと思います。
来年のお正月はぜひ、家族や大切な人たちと一緒にお屠蘇に挑戦してみてください。
ピックアップ商品
甘辛淡麗に偏りのない中庸タイプで、幅広い料理に合わせやすいお酒。
飲むほどに親しみがわく、飲み飽きしないさらりと深い味わいです。
白鶴伝統の味をぜひ一度ご賞味ください。
灘本流の技が冴える、伝統の味わい。
飲むほどに親しみがわく、豊かな味わいの正統派「灘酒」です。
本醸造ならではの円熟した豊かな香りがあるので寒い季節には燗で飲むのにぴったりです。
酒造好適米を70%まで磨き上げ、時間をかけてじっくり醸造した特別純米酒。
縁起の良い金箔を加えているので特別な日のお酒としてピッタリです。
芳醇で風格のある逸品、洗練された味わいが特長です。
白鶴オンラインショップには季節に合ったおすすめの商品がたくさんあります。
お屠蘇をご家庭で作ってみたい方や、お正月にみんなで飲むお酒を探している方はぜひチェックしてみてください。